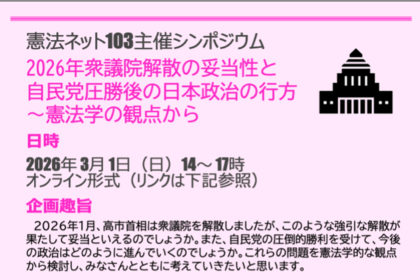小林 武 (沖縄大学客員教授・弁護士)「辺野古最高裁9.4判決と代執行訴訟をめぐって」<2023.10.27 憲法研究者有志の緊急声明資料>
1 国と県の間の辺野古訴訟の本質 : 国の圧制に対する県・県民の不服従抵抗
辺野古をめぐる国と沖縄県の間の訴訟は、巷間弁えのないまま語られるところの、県による勝ち目のない濫訴といったものではけっしてない。
この訴訟の根本的な責任は政府にある。わが国の公権力担当者に民主主義と地方自治への誠実性があるなら、沖縄におけるこの間の衆参各選挙・地方政治の選挙、とりわけて3度にわたる知事選と県民投票に明瞭に刻まれた民意に従って、米軍辺野古新基地の建設は取りやめるのが憲法上の要請である(95条が「一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。」と定める住民意思による直接決定の法理は、辺野古基地建設の是非についても当然に妥当する)。ところが、国は、司法をも巻き込む権力総動員態勢をとって建設強行を図ってきたのである。ここに問題の本質があり、国が見せているものは、法治国家の姿ではない。これに対して沖縄県は、住民の福祉確保を最大の任務とする自治体として、県民の意思に応えて不屈の努力を尽くしているのであり、訴訟における国への対応は、むしろ攻勢的なものであるより、不服従抵抗こそがその本質であるといえる。
沖縄県・沖縄県民のこうした姿勢の背景には、沖縄戦での阿鼻叫喚の地獄、米軍統治下における人間の尊厳蹂躙の苦悩の共有があり、施政権返還後も生命と平和を守るために努力してきた共通の体験がある。この歴史の中で培われた人々の連帯が財産となって、辺野古のたたかいにも受け継がれているといえる。
この度の代執行訴訟に至る過程において、県は、最高裁9.4判決を背景にして基地建設工事の承認を迫る国・与党勢力に押し込まれ、断崖絶壁に立たされていた時期があり、当時の知事の眉間の皴は深かった。しかし、国が是正指示の承認期限だと設定していた10月4日、県はついに承認することはできないとの態度を明確にし、翌5日の国による代執行訴訟の提起に対しては、11日に「応訴」を表明した。知事の表情にも明朗さが戻った。それを支えたのは他ならぬ主権者県民である。逆に、国こそ代執行の暴挙を選択せざるをえないところに追い込まれたのだと、私は考えている。
この辺野古基地問題は、その根源は日米安保体制から発している。そもそもここで争われているのは「米軍」新基地の建設の是非であるが、日本政府は、日米安保条約・地位協定を憲法の上位に置いて、米国に提供する基地の建設のために沖縄県民を強権的手段を講じて抑え込もうとしている。独立国家にあるまじきこうした政府の姿勢こそ問われなければならないものである。
2 最高裁9.4判決の不当性
(1)司法の本来の役割を放擲した空洞判決——-実質的争点の判断なし
最高裁9.4判決の判決文は、その政治的影響力の強さとは似つかわしくない、意外なほど短いものである。A4判で5枚、全文を掲載した沖縄2紙でならわずか3段に収録されており、「判決要旨」かと見紛うほどである。しかも、最高裁自身の見解は、精々最後の数段落に示されているにすぎず、木で鼻を括った感のする作品である。
そうであるのも、この判決は、国交相(国土交通大臣)の是正指示が適法であるとする根拠を、行審法(行政不服審査法)の―すぐ後に述べる、きわめて恣意的な―解釈に求めるのみで、県側が主張した、軟弱地盤などから生じる実質的問題については一切触れなかったことに因る。つまり、最高裁が判断したのは、《沖縄防衛局は、行審法にもとづいて、国交相に知事のした不承認処分の取り消しを求める審査請求をおこなったところ、国交相は、不承認を違法として取り消す裁決をした。それゆえ知事はこの裁決に拘束され、設計変更を承認する義務を負う。よって、国交相が知事に承認を求めておこなった是正の指示は適法だ》というに尽きる。こうした解釈は、行審法を歪曲して導き出したものである。
すなわち、行審法の最重要の目的は、国民の権利利益の簡易迅速かつ実効的な救済を図るところにあり、裁決に拘束力が認められているのもそのためである。これが公法学の通説であり、法律の世界における常識である。しかし、政府による筋書きは、公権力を担当する機関である防衛省沖縄防衛局が「国民」の顔をして「審査請求人」に成りすまし、同じ行政庁である国土交通省に対し、沖縄県知事のした不承認を取り消す裁決を請求し、国交相はそれに応じた裁決を出したのである。世間はこれを「茶番」と嗤って相手にしない。それにもかかわらず最高裁は、このような制度の悪用について、たしなめもせず黙認した上で、国交相の裁決を絶対視し、沖縄県が司法をとおして抗うことを許さないとする論理を立てたのである。そして、これは、ひとり沖縄に限らず国がすべての地方自治体に押
し及ぼすことのできる、自治体統制の支配の論理を最高裁が宣言したものであることに留意しておきたい。
この判決は、それ以外の、肝心の実質的な争点については、判断をすべて回避している。まず、先に述べたように、国が、本来国民の権利を救済するために設けられた行審法の制度を、国民に成りすまして利用することが許されるのかは、判断に入るに先立つ根本問題であるが、これを素通りしている。
そして、県側が、専門的・技術的な知見をふまえ、公有水面埋立法(公水法)にもとづいて詳細に主張したのは、軟弱地盤(マヨネーズ状態のもので、水面下90mのところに広がっている)に工事をすることについて安全性の確保が顧慮されているのか、絶滅危惧種のジュゴンの生育環境保全のための措置、また地盤の盛り上がりに対応した措置がとられているのか、2013年の当時の仲井眞知事による承認から20年、さらに完成までの年月が国にも正確には見通せないような辺野古の埋立てが、果たして公水法の定める「国土利用上適正かつ合理的」という要件を充たしているのか、総じて、国側の変更承認申請は「正当な事由」にもとづくものであるといえるのか、の各項目であった。最高裁は、これら各項目を上告理由として受理していたのであるが、判断は一切せず、行審法がすべてだとして国の強権的な措置を追認したのである。
このような、防衛省の基地建設に県が不承認とした理由について実質的審査を一切おこなわずに、その主張を行審法を恣意的に適用することで斥ける9.4判決は、形骸だけの空洞判決というほかなく、基地建設で争われている真の問題を何も解決しておらず、判決の根拠も将来覆される可能性がある。県の主張は、今なお実質的に生きているのである。
最高裁判決の内容は以上のようなものであったが、それが裁判官(小法廷は5名)全員一致の判決だったことも手伝ってか、各報道機関は(沖縄のものも含め)「知事は工事の設計変更を承認する法的義務を負った」と報じたが、これは必ずしも正確な理解ではないことに留意しておきたい。この判決は、是正指示の取り消しを求める県の請求を棄却したに過ぎず、承認することを義務づける法的効果をもつものではない。知事は、国交相の是正指示を承認するか、承認を明示しない不作為によって、あるいは明示してこれを拒否するか、それとも別の理由にもとづく不承認・撤回をするかの態度決定を義務づけられたにすぎない。つまり、是正の指示は、知事に承認を強制する執行力を備えたものではなく、知事は判決に従わないことも可能であって、そのことは、国と地方の対等性を基本とした今日の地方自治の原理から出るものである。
最高裁に従わない知事は法治国家の反逆者だ、といった類の論調が国政与党の政治家などから今も出されているが、弁えを欠いた謬論である。現に知事は、承認の意思表示をしないまま、米軍辺野古新基地建設の不条理を国際社会に訴えるべく、国連人権理事会(スイス・ジュネーブで開催)に出席し、帰国後も、すでに述べたように、国交相が承認期限だとした10月4日に至るまで「承認は困難」との態度を貫き、その後の国による代執行訴訟の提起には、応訴で対抗した。これは、「最高裁判決への許しがたい不服従」でも、「地方行政の長としての義務違反」でもさらになく、地方自治を憲法原理のひとつとしている現在の法治国家のありようによく適った選択なのである。知事がこの選択をしたことで、県民は、今後も、米軍辺野古新基地建設に対して、政治的・社会的阻止運動はもとより、裁判による異議申し立てをも一層前進させる豊かな可能性をもち続けることになったのである。
(2)最高裁判決の企図したもの――国家意思の積極的貫徹
最高裁9.4判決は、知事の不承認処分の違法性について実質的審理をしないまま、行審法についての形式的な(しかもきわめて恣意的な)解釈のみで、国交相のした是正の指示を適法と断じた。こうした判旨は、法理的な説得力は待ち合わせておらず、判例としての理論的価値も低い。それにもかかわらず、最高裁があえてこうした判断手法を採ったのは何故か。これは、少し踏み込んでおくべきテーマであろう。つまり、最高裁の側に、明瞭な意図ないし司法としての戦略が込められているものと考えなければなるまい。
これにつき念を押しておくならば、最高裁の論理は、《行審法にもとづいて国交相が出した、知事の不承認処分を違法として取り消す裁決に知事は拘束されるから、地方自治法にもとづいて国交相が知事に宛てた是正の指示は適法だ》というものであった。しかし、行審法上の審査請求と地方自治法上の是正指示の取消訴訟は、まったく別個の制度であって、審査請求から出た裁決の拘束力が是正指示の取消訴訟に及ぶことはありえない。それゆえに、原審(福岡高等裁判所那覇支部、2023年3月16日判決)も、是正指示の違法性を裁判所として審理し、その際に、是正指示の取消訴訟における司法審査の制度趣旨について、「地方自治体の長本来の地位の自主独立の尊重と、国の法定受託事務に係る適正の確保との間の調和を図る」ところにある、と述べていたのである(原審判決の結論には同意できないが、この論旨自体は正当である)。
最高裁は、こうした確立した法理を蔑ろにして国優位の姿勢をとおしたわけであるが、結局、その論理は、内容の乏しい空虚な形式論に堕したものであった。同時にそれは、明確な目的、つまり、国家のありよう――ここでは、安保体制の下での米軍のための新基地建設――にかんしては自治体に容喙させないという強い国の意思を、司法をとおして表明し、社会過程に貫徹させようとしたものといわざるをえないのである。
わが国裁判所、とくに最高裁判所のする司法判断については、その「消極主義」が指摘されている。違憲とされるべき立法など国家行為にかんして最高裁が沈黙を守り、その結果、わが国戦後裁判史では違憲判決がきわめて少ない。同時に、最高裁は、憲法判断が事案解決上必要でないケースでも進んでそれに踏み切り、もって政治から期待されている役割を果たすことが少なくない。
そして、今般の最高裁9.4判決は、――憲法判断の事例ではないが――最高裁が司法に期待されていると自ら考える役割を果たしたといえよう。まさに、「政治的積極主義」の判決なのである。
3 県の主張はなお生きている
最高裁辺野古9.4判決は、政治、とりわけ時の政権の要請から自律的でありえない司法の姿を映し出した判決であった。またそれゆえに、この判決は、裁判の実質的争点を解決しえない脆弱なものとなった。国は、結局、代執行という法治国の原理に馴染まない非常の制度、つまり最悪の手段を採らざるをえなかったのであり、それは、法理上も、政治道理の上でも、国の敗北といえるのではあるまいか。
代執行とその後の局面では、県と県民は、玉城デニー知事もよく口にする「いばらの道」を、より大きな荷を背負って歩むことになる。しかし、この度の、国の権力総がかりの圧力の中でも、県と県民は基地建設を承認して国に屈することはなかった。力づくで不条理を押しつけられはしたが、自ら屈することはしなかった。そこには今後の展望がしっかり確保されている。最高裁判決は、県を敗訴としたものの、県の主張を実質的理由をもって斥けることはできなかったのでるから、県民に支えられた県の主張は、なお生きている。県にとって、その前途は、新たな訴訟の可能性も含めて、豊かに広がっているのである。沖縄戦とその後の過酷な歴史を生きた県民は、その代表者にふさわしい実質をもつ知事を支え、ともに、基地のない平和な沖縄の実現に向かって歩み続けるにちがいない。
以 上

「あいちトリエンナーレ2019」における河村市長・菅官房長官の「表現の自由」侵害行為に抗議する憲法研究者声明 
憲法ネット103発足1周年記念シンポジウム 憲法9条に適合的な非武装による安全保障の方法論とは‐ジーン・シャープ「市民的防衛」について 
「安保法制」と9条改憲( 清水雅彦 日本体育大学・憲法学) 
飯島滋明「21世紀日本に元号は必要か」