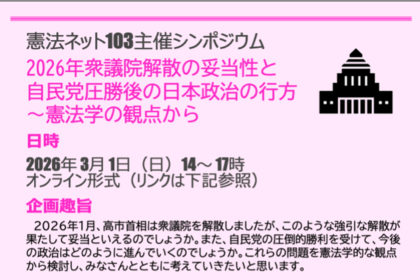日本国憲法74回目の施行記念日に
菅原 真(南山大学教授)
私たちの国民代表は、憲法前文に記されているような「正当」な選挙によって選出されているといえるのであろうか。
今年4月25日、野党系候補が3戦全勝した衆参両院の補欠選挙・再選挙の投票率は3~4割であり、衆議院北海道2区と参議院長野選挙区ではそれぞれ過去最低記録を更新した。前者の投票率は30.46%と、衆院選挙史上過去2番目の低投票率であった。その要因として、マスコミ各紙は、与党が候補者擁立を見送ったことによって有権者の関心が全般的に低かったことに加え、新型コロナウイルス感染拡大の影響が作用した可能性を指摘する。選挙期間中に不要不急の外出自粛要請が出された札幌市内では、候補者は選挙活動を自粛し、有権者も積極的に投票所に足を運ぶことができなかったというのである(選挙権行使ができない新型コロナ感染者の法状況については、別途、毎日新聞3月24日配信記事「コロナ療養者は投票できない? 感染防止か選挙権か自治体板挟み」を参照せよ)。
しかし、新型コロナの影響を認めるとしても、そもそも主権者たる「日本国民」の約半数しか投票に行かないという「民主主義の危機」は近年ずっと続いているのである。現行憲法下で行われた衆院選挙の投票率は、実は1993年までは70%前後で推移してきたのが、1996年以降60%を切り、2014年および2017年の直近2回は50%台前半にまで低下した。その要因として、日本経済新聞4月28日配信記事「衆院選投票率、直近は50%台前半 小選挙区制のもと低下」は小選挙区制の導入があることを正しく指摘する。その1996年総選挙は小選挙区制比例代表並立制が導入されて初めて実施された選挙である。同記事は、「小選挙区であってもせめぎ合いがあれば、有権者の関心は高まると言える」と指摘するが、そもそも小選挙区制は死票が多いという問題点があり、あたかも前近代の身分制社会の如く、代々政治家の家系に属する人物が地盤・看板・かばんを継承する「勝てる候補者」(大抵は男性)として小選挙区選挙に立候補し、当選している例がいかに多いことか。その結果、小選挙区制の下では選挙に「勝ちづらい」女性候補者は、大政党からはそもそも立候補させてもらえない。「民意の反映」ではなく「民意の集約」を目的とした小選挙区制を導入したのは、1990年代の「政治改革」によるものだが、そこで生み出された民意(得票率)と議席(議席数)との大きな乖離の問題は、今こそ再認識されるべきであろう。ようやく日本でも、2018年5月に「政治分野における男女共同参画推進法」が施行されたものの、「ジェンダーギャップ指数2021」では、いまだに世界156カ国中120位(政治分野は147位)いう地位に甘んじているのが日本の現状である。
女性だけではない。若者の投票率や立候補者数も極端に低い。2017年総選挙では、20歳代の投票率は33.85%であった(18歳・19歳は40.49%)。未来を担う若者世代の「民主主義」は、選挙のレヴェルのみに注目すれば、風前の灯となっている。これは、高校生が「模擬投票」を練習することによって何とかなるような問題ではない。中等教育・高等教育において、具体的な政治イシューを多角的視点から議論し、各政党や候補者が何を主張し、どのような処方箋をもって公約に具現化しているのかを検証するなど、単純な〇×的議論でよしとするのではなく、未来社会を展望する政治哲学的な観点を大切にするような、中身のある「主権者教育」が大切になるであろう。国内で井の中の蛙になるのではなく、諸外国との同世代の若者と「政治」について意見交換したり、議論したりする「国際性」も大切である。欧米諸国では若い世代が政治家として活躍していることも、しばしば日本でも紹介されている。公選法が規定する選挙権年齢と被選挙権年齢の大きな差も、今後、法改正によって解消すべきであろう。
国政選挙においては、「違憲状態」判決が相次ぐ小選挙区間の一票の較差・不平等問題、選挙期間中の選挙活動を不当に規制する公選法の問題や、特定の国籍や民族を排撃するヘイトスピーチを行う候補者の「自由」を抑制するための手段の問題、また地方選挙レヴェルにおいては、住民として生活し、税金も納めながら選挙権を持たない永住外国人市民の参政権の問題など、この分野で議論中の憲法問題は多数存する。あらためて日本国憲法の下における「民主主義」の在り方や「正当な選挙」制度の在り方を、市民の皆さんとともに考えていきたい。