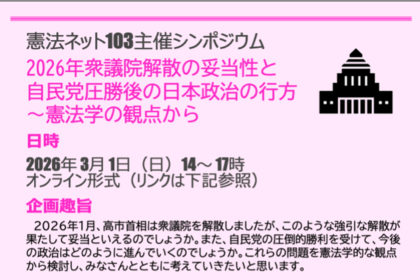≪歴史の重みvs「選択なんて贅沢?」という憲法の重み≫
長峯 信彦(愛知大学教授)
2021年4月、1年ぶりに対面授業が戻った。久しぶりに学生たちの顔を見ながらの授業はやはり違う。新鮮だ。私が今担当している「憲法・基本的人権」は520人の授業だが、新型コロナウィルス感染対策のため、三分割開講にし3コマでやっている。大変疲れるが、楽しい。今年も学生たちに問うた。
「なぜ、自分で就職活動して、就職先を自分で選ばなければならないと思う?」(日本ではあくまでも異性愛結婚しかできないという限界があることを注釈し、且つ、結婚は別に「しなければならない」ものでは全くないんだと告げた上で)「なぜ、結婚相手って、自分で苦労して探さなければならないと思う?」
学生が口々に言う。
「そうなんですよね。自分で就職活動しろ、自分で就職先を選択しろって、すごくしんどいです。結婚相手だって、自分で苦労して探せって言われても、たぶんムリっぽいと思うんです。いっそ、神サマか魔法使いが用意してくれたらな、って時々思います。」
「自分で選択しろなんて言われても、ただでさえ一つも内定取れていないのに、ただでさえカノジョもできたことないのに、選択なんて贅沢、そもそもあり得ないじゃないですか」
さて、コロナ禍で、多くの人がギリギリで生きている。学生たちもオンライン授業で疲弊しきっている(教員も)。そんな中で、「選択なんて贅沢」という一言が厳しく胸に突き刺さる。確かに、諸々苦しい中では、「選択」なんて“贅沢”にしか映らないのだろう。
では、憲法22条「職業選択の自由」も、憲法24条「婚姻の自由/配偶者選択の自由」も、結局は「選択できるだけの・余裕のある人々の特権的自由」、いわば“ブルジョワ的贅沢”なのだろうか。
ここで想起したいのは、人類何千年の歴史の中で、有名な権力者たちの栄枯盛衰は「見えるオモテの歴史」を形づくってきたが、その歴史を、歯を食いしばって無言で支えてきたのは、「見えない陰の歴史」に消えて行った無数の一般庶民(多くは農民)だったという事実である。権力者に命ぜられるまま、農民は年貢を納め、町民は税を支払う。農民は基本的にその土地に縛り付けられ、農民の息子はどれだけ嫌でも農民を継がなければならず、大工の息子はどんなに剣術が上手でも大工にならなければならない。
人類の大部分にとって、職業とは、そもそも「選択」できないものだったのである(居住場所もまたしかり)。それは支配者の側も同じだった。殿様の嫡男に生まれた男子は、仮にモーツァルトのようなピアニストになりたくても、絶対に殿様に「ならなければならなかった」のだ。つまり、「身分制(血筋・家柄)のしがらみ」にがんじがらめに縛られていたのが職業だった。選択の自由は、そもそもない。
結婚は、それに比べれば多少は「本人の意向」が聴き入れられる場面もあったかもしれない。しかし、たとえば日本の場合、身分が高ければ高いほど、それは自由ではなくなっていく。斉藤道三の娘(帰蝶)と織田信長の結婚に象徴されるように、結婚とは基本的に「親(特に父親)が決めるもの」だった。このことは、時代が下っても、身分が下がっても、あまり変わらなかったと思われる。自分のパートナーなのに、「身分制(血筋・家柄)のしがらみ」に縛られ、多くの場合、本人の純粋な選択ではなかった。
今、私たちの日本国憲法には、人類何千年の歴史の中でその大部分だった農民たちが、嫌でも土地に縛り付けられ、嫌でも農民を継がなければならなかった、その歴史の重み・うめき声の集大成とも言うべき内容が、憲法22条「居住・移転・職業選択の自由」となって存立している。
同時に、自らの尊厳と人格的生存に深く関わるはずの「結婚」が自由にできず、しかも男尊女卑の中で悲しみをこらえにこらえてきた無数の女性たちの涙と悔恨の総結集--歴史の重み--とも言うべき内容が、憲法24条「婚姻の自由/配偶者選択の自由」となって結実している。
日本国憲法は、徹底して「身分制のしがらみとの決別」を宣言する、「個人の尊厳に基づく、個人の自由選択」の法典である。しかしそれは同時に、苦しみの中にあって余裕のない人々にとっては「選択という重荷」を課されてしまっている、ように映ることも事実だろう。受け止め方は、人によってはけっこう難しいところだ。現在はもちろん身分制社会ではないものの、「選択できない苦しさ」「選択どころではない貧窮」に喘いでいる多くの人々(学生に限らない)がいることを--≪ 歴史の重み ≫と重ね併せ--、私たちは決して忘れてはならないだろう。
しかし同時に、やはり、「個人の尊厳」と「自由な選択」こそは、日本国憲法の原点であり存在意義である。まさに、「憲法の重み」ではないだろうか。私たちはこの≪ 重みの正しさ ≫を、果たして次代の若者たちや市民に正しく伝えていけるだろうか。そしてその際、どう伝えていけばよいだろうか。コロナ禍にあって、私たち憲法研究者自身もまた、さまざまな「選択」に問われている。