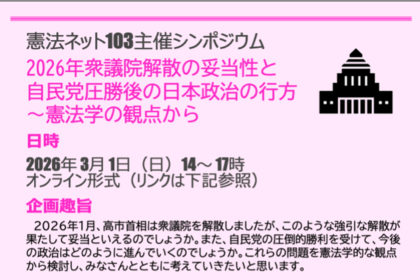東アジアで生きるという選択肢
稲 正樹(元国際基督教大学)
1「集団的自衛権問題研究会」というグループが「敵基地攻撃能力ではなく北東アジアの軍縮協議を」という提言をしています(世界2020年10月号)。以下のような内容です。
(1) 北東アジアにおける核・ミサイルの脅威に対処する軍縮・軍備管理の協議を発展させること
・過去11回行われてきている日中軍縮・不拡散対話をさらに強化し、中国を含む地域的な核・ミサイルの軍縮と軍備管理の枠組みを追求すること。
・米朝交渉と南北交渉の再開を支援し、2018年4月の南北板門店宣言と同年6月のシンガポール合意に盛り込まれた朝鮮戦争の終結と朝鮮半島の非核化の目標に向けた国際的な行動を促すこと。
・2005年9月の六者協議共同声明に則り、北東アジア地域の持続的な安全保障体制について協議するための米、ロ、中、韓、朝、日の六カ国による北東アジア軍縮・軍備管理協議の場を設けること。
・これらの協議を通じて、まずは地域のミサイルに関する情報交換を進め、次に中距離・短距離ミサイルの管理と削減に向けたロードマップ策定をめざすこと。協議に参加するすべての国のミサイルの開発、保有、配備が議題になるべきであり、その中には在日米軍や在韓米軍のミサイルも含まれるべきである。
・こうした地域的なミサイル管理の協議と並行して、北東アジア非核兵器地帯構想に関する議論を深めること。
(2) 日本は専守防衛を堅持し、これを変更すると受け止められるような政策を止めること
・日本政府は「攻撃的兵器の不保持」原則を明確化・厳格化すること。
・日本政府は「敵基地攻撃能力」を構成し得るあらゆる兵器の導入や開発を中止すること。その中には、長距離巡航ミサイル、GPS精密誘導爆弾、巡航ミサイル・トマホーク、地中貫通弾などの導入、高速滑空弾や極超音速ミサイル等の開発、空母「いずも」「かが」の本格空母への改修、F35戦闘機の大量導入などが含まれる。
・政府は辺野古の基地建設をただちに中止し、普天間飛行場の運用停止と無条件返還に向けて、米国との交渉を進めること。
・南西諸島において、地対艦・地対空誘導弾部隊の配備やF35戦闘機の離発着訓練を前提とする自衛隊基地建設や、島嶼防衛を念頭に置く日米共同訓練を中止し、地元住民との丁寧な話し合いの場を設けること。
(3) 世界的な核軍縮の進展を後押しすること
・米ロの新戦略兵器削減条約(新START)の延長・更新について交渉が続けられているが見通しは立っていない。米国は中国を巻き込んだ新条約をめざす意向といわれるが、中国の不関与を理由に新STARTを失効させてしまえば、昨年の長距離核戦力(INF)全廃条約の失効に続き国際的な核軍縮管理への深刻な打撃となる、米ロは新STARTを少なくとも延長させ、さらなる核兵器削減を確実にしつつ、時間をかけて中国を含む多国間の軍縮・軍備管理枠組みを形成すべきである。
・日本と韓国は2017年に成立した核兵器禁止条約に署名し、もって世界的な核軍縮の機運を高めるとともに、北東アジア地域における核の脅威削減に貢献すること。
(4) 気候変動や感染症が「人間の安全保障」に深刻な脅威をもたらしている現状を踏まえ、安全保障政策の包括的な見直しを進めること
・北東アジア諸国間で、新型コロナウィルス感染拡大とその対策に関する情報交換、経済危機や社会不安への対応、ワクチン開発や普及などの保健分野での連携を強化すること。国家予算における軍事支出を削減して医療・保健に転用し、それらの措置についての情報交換を強めて信頼醸成を図ること。
・北東アジア諸国間で、感染症対策、気候変動や災害対応など「人間の安全保障」の分野における協力関係を強化すること。その際、市民社会の参加を積極的に促すこと
2 いずれももっともな提言であり、日本と東アジアにおいて平和構築を進めていくための行動指針を示しています。いま「新しい戦前の始まり」と言われるような時代状況の中で、戦争への道ではなく、東アジアにおいて平和をもたらす展望を示すことが必要です。同時に、東アジアにおける分断構造を克服するために、根本的な自己改革が求められているのではないでしょうか。
「地域統合史のなかの国際協調主義」という論文において、川嶋周一は「長い20世紀を生きているアジア」についてこう指摘しています。
「ヨーロッパの中軸たる独仏関係は、対立の極地の末に戦後国際協調を進めたが、北東アジアの主要国である日中韓の三国の国際協調は、いまだ入口にすら立っている状態ではないのが現状であろう。アジア諸国が抱える課題の奥底はまだまだ深い。それは、ヨーロッパが『短い20世紀』(ホブズボーム)を生きたのに対して、アジアは長い20世紀を(未だ)生きているからである。イギリスが生んだ歴史家トニー・ジャットは、ホロコーストの事実を受け止めることが戦後ヨーロッパ世界に入るための通行証だと記した。アジアにおいて、戦後世界に入るための通行証は何か。そのコンセンサスができていないこと自体、アジアにおける戦後世界は実はヨーロッパ的意味においてまだ始まっていないことを教えている。それは、アジアに生きるわれわれが未だ長い20世紀の時代を生きている証左なのである」(川嶋周一「地域統合史のなかの国際協調主義−ヨーロッパとアジアの比較と交錯」笹川紀勝(編著)『憲法の国際協調主義の展開』敬文堂、2012年)。
3 かつて、立命館大学の君島東彦さんの論文において、以下のような韓国の歴史学者白永端(ペク・ヨンス)の東アジア平和論を教えられました。
東アジアにおいては、世界史的な脱冷戦の状況にもかかわらず、依然として分断が継続している。韓国の一部の研究者は、東アジアのこの状態を「東アジア分断体制」としてとらえた。それは、大分断体制、すなわち中国と日米同盟の間の分断と、その大分断と密接に関連しつつ独自性をもった小分断体制(朝鮮半島の分断、日本本土と沖縄の分断、中台の両岸関係)で構成された重層的構造を巨視的観点から説明する概念である。この体制が1949年の中華人民共和国の成立とともに形成されて以来今日まで続いている。
東アジア分断体制を作動させてきた要素は、地政学的緊張、政治社会体制の異質性、歴史心理的間隙である。このうち、歴史心理的間隙(歴史心理的溝)という第三の要素、とりわけ日清戦争以来持続してきた戦争と冷戦期を経て、中国と日本のあいだに歴史心理的分断が凝結し、拡大再生産され今日まで影響を及ぼしていることを白永端は「分断構造」と捉えている。大分断構造のなかで占める中国の位置と役割に注目し、現在東アジアで高まっている相互嫌悪感情の悪循環は、単なる相互交流と協力の増加だけでは解消されにくい構造的な矛盾の所産である。「体制」ではなくて、よりダイナミックな「構造」としてとらえると、分断を解体・克服するアクターと道筋が見えやすくなる。
東アジア分断構造は、歴史的に3つの時期に分けることができる。中華帝国(清)の朝貢体制の時期、次に大日本帝国の支配の時期、そしてパックス・アメリカーナの時期の3つ。現在の大分断構造には、朝鮮半島の南北分断、日本本土と沖縄の分断、中台の両岸関係という3つの小分断構造が付随している。まず、朝鮮半島は。かつては日清、日露の対立の場であり、大日本帝国の植民地であり、冷戦の最前線だった。現在は、米国・日本から見ても、中国から見ても、「緩衝地帯」としての役割を押し付けられている。次に沖縄は、琉球併合以来、大日本帝国の「捨て石」であり、パックス・アメリカーナにおける米軍基地であり、中国の第一列島線である。そして、台湾は、日清戦争後、大日本帝国の植民地となり、その後、中国内戦と国際冷戦という二重の戦争の下にあった地域である。
白永端はまた「核心現場」という考え方を導入している。核心現場とは、東アジア分断の葛藤・矛盾を集中的に体現している場所で、上記の小分断の場所は典型的な核心現場である。これらの核心現場において、小分断を克服しようとする努力から生まれるダイナミズムが東アジア全体に波及し、大分断の解体・克服に影響を与えることが期待される。また、日本・韓国・北朝鮮の間にある歴史心理的な分断・溝を克服する努力もまた要求される(白永端『共生への道と核心現場−実践課題としての東アジア』法政大学出版局、2016年)。
4 中国、北朝鮮、韓国、台湾といった諸国とともに東アジアにおける平和と相互協力
・理解の地域を作り出していく新たな構想とそれに向けての地道な努力を積み重ねていくべきだと考えます。
酒井直樹は『ひきこもりの国民主義』(岩波書店、2017年)において、以下のように指摘しています。
アメリカの属国となって日本国民がおかれたポスト・コロニアルな条件=日本帝国は崩壊したが、日本の人々(戦後も日本籍をもち続けた人々)の帝国意識はじつは崩壊しなかったのではないか。1990年代以降に日本社会が直面しているのは、まさにポスト・コロニアル状況だ。経済的独占や政治的抑圧の制度としての植民地主義が失われたにもかかわらず、国民的同一性の核としての植民地主義が存続しているとき、人々が脱植民化のために自己変革を遂げるには「恥の体験」を経験しなければならないはずだ。ところが、この20年間、日本社会ではかえって「恥の体験」を恐怖し、「恥の歴史」を否認する傾向がますます強くなっている。日本社会が「恥知らず」になってきている。脱植民地化を拒絶する国民主義は、疑いもなく、「ひきこもりの国民主義」の一面を表していて、国際社会から「ひきこもる」」傾向と脱植民地化を拒絶する態度とは、『ひきこもりの国民主義」の表裏をなしている。
私たちは、下請けの帝国意識を解体し、脱植民地化をなしとげ、東アジアで生きるという誓いをあらたにすべきではないでしょうか。