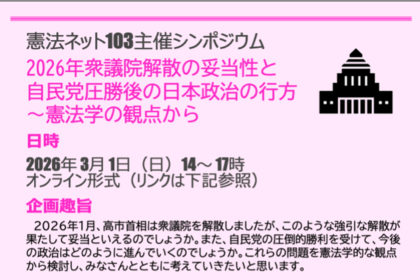第193回国会の衆議院憲法審査会の「日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件(国と地方の在り方(地方自治等)」(2017.4.20)における、小林武参考人(沖縄大学客員教授)意見
○小林参考人
小林でございます。
本日は、貴重な機会をいただきまして、会長そして委員の皆様に感謝いたします。
私は、国と地方のあるべき関係について、憲法上の基本的な論点を検討した上で、特に沖縄を視野に入れて意見を述べることにいたします。
憲法審査会の権限を定めている国会法第十一章の二に基づいて本日の主題を考えますと、憲法第八章地方自治と、憲法の附属法とされる地方自治法等の基本法制を対象として検討を加え、それを通して改憲の要否を論じることが求められていると思います。
それにつきまして、私は、現在、日本国憲法第八章の改正を不可避とする事情は存在しない、それは条文の規定の仕方も含めて存在しておらず、また、それを要求する世論は多数ではなく、かえって、これを完全に実施するための方策を講じることこそが政治に求められていると考えます。したがって、また、憲法改正提案に対していわゆる対案を出すべしという議論についても、現行憲法の完全実施こそ現在における最善の対案であると思う次第であります。
以下に理由を述べますが、それに先立ち、本審査会が日本国憲法の改正に関して、九十六条に基づく厳密な改正を審議する場であることに特に留意して、いわゆる憲法改正の限界について一言触れておきたいと思います。
すなわち、憲法改正手続によりさえすればどのような改正も法的に許されると説く無限界説もありますが、限界があると解するのが、戦前戦後を通して憲法学界の通説であります。
それによれば、人権宣言の基本原則や国民主権、国際平和の原理、そして憲法改正の国民投票制などについては、九十六条による改正は許されないことになります。このことに照らすならば、二〇一二年に出された自由民主党憲法改正草案は、多くの箇所で改正限界に抵触しているとの疑念を禁じ得ないものであります。
ちなみに、この二〇一二年案と同程度に限界を超えていると思われるものであったところの二〇〇五年の自民党案は、改正草案とは名乗らずに、新憲法草案としておりました。これは示唆的であります。
改正限界を超えた憲法の改正は、法的に無効と評価されるものでありますから、この憲法改正限界の問題には、当審査会におかれましても格別の留意が払われてしかるべきであると私は考えます。
以上を前置きして、国と地方のあり方という本日の主題の検討に入りたいと思います。
我が国におきまして真正の地方自治制度をもたらしたものは、ほかならぬ日本国憲法であります。明治憲法は地方自治に関する規定を備えておらず、地方制度は法律上のものでしかなく、その編制ないし運営は立法政策上の問題でありました。それで、地方自治体は実質上中央政府の下請機関となり、また、住民の手による本来の自治は実現されるべくもなかったわけであります。それに対して、日本国憲法が地方自治に憲法的保障を与えたことは、憲法原理上の根本的な変革であり、まさに画期的な意義を有するものであると言わなくてはなりません。
ただ、憲法制定過程で、連合国軍総司令部が提案した地方政府構想は、日本政府、とりわけ内務省の強硬な抵抗に出会います。それは、明治憲法時代の徹底した官治行政の仕組みと中央集権の理念を新憲法下でもできる限り維持しようとするものでありました。そのことが、制定されたただいまの第八章にも少なからず反映していることは否めないと思います。
とはいえ、憲法第八章は、そのような制約を加えられながらも、民主主義政治の基盤としての地方自治を実現し、住民の人権を確保する規範としての内容を十分に備えたものとなっております。
そして、この第八章地方自治が、第二章戦争放棄とともに、明治憲法には存在せず、日本国憲法に新規に導入されたものであることを重視しておきたいと思います。つまり、この二つの章は、明治憲法下で進められた官治主義と軍国主義を排除するものとして不可分一体の双子の形で誕生したものであります。
このようにして、第八章地方自治は、まさに平和国家の建設にとって不可欠の章であると言わなくてはなりません。
それゆえに、逆に国が軍事へと傾斜するとき、地方自治は戦争遂行の阻害物とみなされます。最近のとても見やすい事例は、改憲の主張として登場している緊急事態条項でありますが、例えば、二〇一二年の自民党改憲案によれば、緊急事態が内閣総理大臣によって宣言された場合、地方自治体の長は内閣総理大臣から必要な指示を受けることになります。地方自治は一時停止されるわけであります。
以上述べましたような憲法第八章が憲法史上に持つ画期的意義を確認しておくことは、今回のテーマの審議に当たって共通の土台となるものではないかと思われます。
今述べましたところから、地方自治は、人民の人民による人民のための政治という民主主義の価値において、国の政治と対等の位置にあると言えます。それにもかかわらず、実際には、中央政府は地方自治を軽視し、その結果、国と地方はあたかも上下主従の関係にあるようにみなされ、中央集権制の弊害が払拭されずに色濃く残されてきました。
この点で、詳しく述べる時間はありませんけれども、一九九九年の地方自治法大改正、ここに込められた国と地方の対等関係を相当前進させる内容は注目すべきであると私は考えております。
さらに、我が国の国と地方の関係を極めて不正常なものにしている要因として、日米安保条約の問題を見落とすことができないと思います。すなわち、それに基づいて日本各地に米軍基地が置かれ、各自治体と住民が負担を強いられており、その負担は住民の生命と人間の尊厳を脅かすまでに至っております。
米軍への基地提供の法的仕組みの大もとにあるものは安保条約でありますけれども、しかし、条約は、住民と自治体の権利、権限を制限し、義務を課す直接の根拠となり得るものではありません。国民代表議会の作品としての法律が必要とされるわけであります。それが原則であります。憲法九十二条が、地方自治体の組織、運営に関する事項は法律で定めるとしているのも、この趣旨であると言えます。
したがいまして、安保条約との関係でも、本来、法律を定める国自身が、地方とその住民の権利擁護について自覚的でなければならないのであります。
加えて、地方自治体は、米軍基地を発生源とする事件、事故のもたらす被害から住民を保護するために、自主立法権を行使して、住民保護条例を制定することができる、また、すべきであると私は考えます。
これは、特に日米地位協定が米軍への我が国の法令の適用を基本的に排除していることにかかわっておりますけれども、日本政府はその改定に進み出そうとはいたしません。それで、地方自治体が、条例によって米軍、米軍人等の一定の違法行為を規制し、もって住民の生命と人権を守ることが求められるのであります。そして、現在、そのことは、とりわけて沖縄で喫緊の課題となっております。
2の沖縄に関する議論に進みます。
国と地方のあり方について、その極端にゆがめられた姿を見るのは沖縄であります。ことし、日本国憲法施行七十年を迎えますが、沖縄については四十五年であることを、まず確認しておきたいと思います。
すなわち、一九四五年四月、沖縄戦で上陸した米軍は直ちに日本の統治権を停止し、それによって大日本帝国憲法の適用は遮断されました。そして、戦争の終了によっても、さらに一九四七年の日本国憲法の施行後も、あまつさえ一九五二年の平和条約発効による日本の法的独立の回復の際にも、その三条によって沖縄は切り離され、米国による占領は変わることなく、憲法は復活しなかったわけであります。憲法の適用のない法状況は、一九七二年の本土復帰まで二十七年に及んだのであります。
沖縄の人々は、日本国憲法のもとへの復帰を望み、幾多の努力を重ねたのでありますが、復帰の実態は日米安保条約体制に組み込まれることを意味しました。その間、地方自治は米国による施政のもとでは存在すべくもなく、また、復帰後も米軍基地が重圧となり続けているのであります。
今日の焦点は、名護市辺野古における米軍新基地の建設にありますが、沖縄県民はこれに一貫して反対しております。
特に、二〇一三年には、いわゆるオール沖縄と言われる、そういう沖縄を挙げての声でありますけれども、オスプレイの配備撤回、普天間基地の閉鎖、撤去、そして県内移設断念を求める建白書を内閣総理大臣に提出いたしました。一月のことでありました。
その年の末に、当時の仲井真弘多知事が、県民への公約に背いて政府に辺野古の公有水面埋め立てを承認したのでありますが、翌二〇一四年、県民はこれを絶対につくらせないことを公約した翁長雄志氏を知事に選びました。そして、同じ年、辺野古のある名護市の市長選、市議選、衆議院の四つの小選挙区選挙の全てにおいて、新基地反対の候補者が推進派の自民党候補者に圧勝する結果となったのであります。
すなわち、地方自治の原則に照らしますならば、この段階で、沖縄の民意を尊重して基地建設を断念するのが、憲法のもとにある政府がなすべき当然の選択であったはずであります。それにもかかわらず、こうした民意を政府が一顧だにしようとしないことは、地方自治をないがしろにするものでありまして、そのもとでは、住民と自治体はみずからの運命をみずから選ぶことはできず、住民は自治を担う主権者として育つ機会を奪われます。つまり、それは民主主義の死滅をもたらすものであると言わざるを得ないのであります。
加えて、沖縄県に対して国がとっている姿勢には、法制度の運用の恣意性が際立っております。事例を限って指摘しておきます。
一つは、二〇一五年十月十三日に知事が公有水面埋立承認の取り消しを行ったのに対して、直ちに沖縄防衛局が行政不服審査法を持ち出して、国土交通大臣に審査請求と執行停止を申し立てたことであります。国土交通大臣はすぐさま承認取り消しの執行停止を決定し、工事は着手されました。
しかし、政府がここで用いた行政不服審査法は、本来、行政の違法な行為に対して、国民の権利利益の救済を図ることを目的とした法律であります。それにもかかわらず、国は、あたかも国民、つまり私人に成り済ましてこの制度を使っております。法の悪用ないし逆用と言わなくてはなりません。
また、今年三月二十五日、知事はいずれ承認の撤回に踏み切ることを明言しましたが、これを受けて政府は、知事個人に対して損害賠償を請求することもある旨表明いたしました。
こうした訴訟は、現行司法制度が本来的に予定している類型にはなじまないものであります。いわゆるスラップ訴訟が企図されているのではないかと思われます。つまり、首長に高額の賠償という懲罰を与えて、住民の側に立つ抵抗行動を控えさせるという萎縮効果を上げることが目的とされているのであります。しかし、国がこうした手法をとることは、地方自治を機能不全に追い込むものであって、許されるものではありません。
もう一つは、政府の法解釈の恣意性であります。これは、新基地建設の岩礁破砕に関してお話を申し上げようと用意していたんですが、時間の関係で省略いたしますので、私のこの拙い文章をごらんになっていただければ大変ありがたいと思います。
結局、沖縄については、特に米軍基地問題を見るときに、政府による法制度の運用は、国、地方の対等関係を真っ当に理解したものとは到底言うことができません。沖縄を、地理的にとどまらず、政治的、軍事的に辺境とみなした措置であるように思われます。つまり、特定の地域と住民に矛盾を押しつけ、苦悩を負わせておきながら、恬として恥じない政治であります。
そして、それは、二〇一一年三月十一日の原発事故で甚大な被害をこうむった福島に対する姿勢にも通底しております。国には、今こそ、憲法の原理と地方自治の原則に基づいてみずからを省みることが求められていると明確に指摘をしておきたいと思います。
結びでありますが、以上の検討からすれば、国と地方のあり方に関して今なすべきは、憲法第八章に改定を加えることではなく、地方自治の保障の原点に立ち返って、これを充実させることであると思います。
その内容は、主要なもののみを列挙いたしますが、一、事務分担に関して、自治体優先、基礎自治体最優先の原則を大前提に、補充性の原則を貫いて、地域社会にとって根幹的な行政を自治体に総合的に移譲すること、二、財政権限の移譲により自治体財源を確保すること、三、行政区画については、現行の二層制を維持した上で、さらに将来、広域性とは逆に、狭域行政の制度づくりに進むこと、四、自治体がみずからの行財政の立案をし、それを実行する公共経営能力を持つようにすること、五、住民が、自治体の政治、政策をつくる過程に参加して意見表明をする地位が保障されることなどがその主な部分になるかと思います。
そして、国と地方のあり方を考える場合に、本日の私の意見で触れた沖縄の問題、また福島の問題を等閑に付してはならないことを繰り返し強調しておきたいと思います。それは、全ての地方の問題に共通する普遍性を持つものだからであります。
憲法審査会におかれましては、地方自治を充実させる課題にこそ力を注ぎ、もって主権者国民の信託に応えられることを強く望みまして、参考人としての意見にいたします。
御清聴ありがとうございました。(拍手)